学生さんおススメ図書のご紹介
本好きの学生さんから皆さまへおススメ図書のご紹介です。
面白そうな本をご紹介いただきました。
貸出できますので、ぜひ読んでみてください。
ご来館お待ちしています。
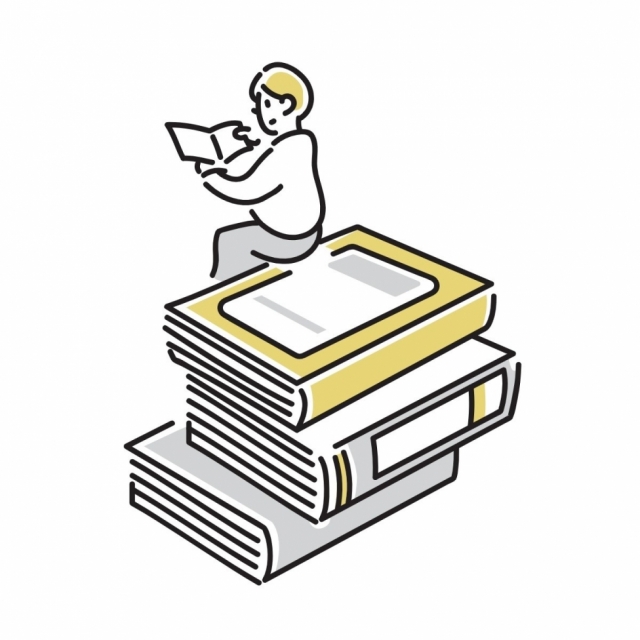
音楽学科 井上里穂さんおススメ
「まよなかの魔女の秘密」
著:岡田淳作 出版社:理論社
「この森でもなければ その森でもない あの森でもなければ どの森でもない こそあどの森 こそあどの森」
不思議な森を舞台に、不思議な住人たちが繰り広げる、不思議なファンタジー。 シリーズ2作目である『まよなかの魔女の秘密』は、森の住人の1人が忽然と消えてしまった…という少しぞっとする出来事から始まります。ミステリーのように進んでいく物語にドキドキ。えっ、それってどういうこと…!?と慌ててページをめくっていくと、物語はどんどん意外な方向に。途中で、自分はミステリーではなく美しい愛の物語を読んでいるのだということに気づきます。 最後にさらりと出てくる一言は、思わず二度見(二度読み)するほど深いです。 "あなたが、あなただから愛してる" こんなセリフはないのですが、そんなセリフが聞こえてきそうな、素敵な物語です。
音楽学科 西川晴さんおススメ
「medium : 霊媒探偵城塚翡翠 」
著:相沢沙呼 出版社:講談社
主人公の城塚翡翠は、翠の瞳と美貌を持つ少女で、霊媒の才能がある。推理作家である香月史郎は、ある殺人事件をきっかけに、翡翠とともに事件を解決するようになる。翡翠の能力と香月の論理を合わせて、二人は次々と難事件を解決し、ついに、一切の証拠を残さない連続殺人鬼と対峙する。その最終話には驚愕の結末が……。
相沢沙呼によって書かれたこの作品は、ミステリランキング5冠を獲得した大傑作である。
この作品の一番の魅力は、「登場人物のキャラクター」にあると私は思う。主人公の翡翠はもちろんのこと、本作には、実在しそうな親近感のある人物がたくさん登場する。特に翡翠はコミカルな部分が際立っており、本作は、ミステリでありながら、シリアスになり過ぎずに読むことができる素晴らしい作品である。
ミステリ愛好家はもちろんのこと、初めてミステリを読む方にもおすすめしたい。
美術学科 山下麻衣香さんおススメ
「ヨーロッパの幻想美術 : 世紀末デカダンスとファム・ファタール (宿命の女) たち」
解説・監修:海野弘 出版社:パイインターナショナル
本書は19世紀末の芸術運動の一つである象徴主義の中から、ジョリス=カルルユイスマンス「さかしま」を出発点として発展した「退廃主義(デカダンス」の作品を、芸術家たちが取り憑かれたように描き出した宿命の女と呼ばれる女たちにフォーカスを当て、海野弘による解説とともに送る作品集である。
海野は、さかしまの一節を引用し、その一説が世紀末デカダンス美術が如何なるものかを語っていると言った。
「精神の快楽と眼の歓びのための作品を求めていた」
この一節は、正しく退廃主義美術のあり方を表現し、同時に私のような精神衰弱の好事家が何故、退廃主義美術を愛するのかを表現していると思う。
象徴主義らしい装飾性に溢れた美しい装丁に目を惹かれ、随所に散りばめられた不穏なモチーフから目が離せなくなってしまったあなたは、きっと仄暗くも美しく、鮮烈で艶やかな美をひっそりと愛する好事家の1人だろう。
そんなあなたに、是非とも本書に触れていただきたいと思う。
ひと度ページを捲れば、悪魔のような女神のような女たちから、扉、遊び紙にまで及ぶこだわり抜かれたデザインからきっと目が離せなくなる。
目眩く幻想美術の旅路へ誘われてみてはいかがだろうか。
美術学科 学生さんおススメ
「欲しくなるパッケージのデザインとブランディング」
編著:パイインターナショナル 出版社:パイインターナショナル
この「欲しくなるパッケージのデザインとブランディング」は、タイトル通り思わず手に取りたくなるような、欲しくなる多種多様のパッケージのデザインやブランディングがたくさん紹介されています。中を開くと、ただひたすらかわいくて洗練されたパッケージがずらりと並んでいるので、ページをめくるたびに思わず「欲しい!」と思わせるデザインに出会えます。
視覚的な要素だけでなく、消費者心理も深く掘り下げているので、デザインが持つ影響力や可能性について新たな視点が得られます。自分が手がけた作品にどう付加価値を与えるか、どのようにしてブランドを表現するかを考えるためのヒントが詰まった内容です。
美術やデザインなどに興味がない学生さんでも、見ていて楽しいですし、文章の少ないアートブックのような構成なので、文章を読むのが苦手な人にもおすすめです。
地域社会学科 学生さんおススメ
「きりこについて」
著:西加奈子 出版社:角川書店
かつて私は、自分自身の容姿に自信がありませんでした。もっと目が大きければ、もっと顔が小さければ…と考えても仕方のないようなことばかり考えていました。そんな時に出会ったのがこの本、「きりこについて」です。
主人公のきりこという女の子は両親からの愛情を受け、自分を「かわいい」と信じて疑わない女の子に育ちました。小学5年生のある日、きりこは好きな男の子にラブレターを渡しました。様子を見ていたクラスメイトにからかわれた男の子がきりこに向けて発した一言が、彼女の絶対的な自信を跡形もなく崩したのです。そんなきりこが、とある人々との出会いを通して、人生で一番大切なことに気付く物語です。
私たちの人生においても、誰かの一言で自信をなくしてしまうような経験は珍しくないと思います。でも、私は私で、あなたはあなたなのです。他の人は関係ありません。そんなことに気付かせてくれる一冊です。ぜひ、自分に自信のない人、自分を好きになりたい人に読んでいただきたいです。
地域社会学科 学生さんおススメ
「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : the real British secondary school days」
著:ブレイディみかこ 出版社:新潮社
「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」という「なんとなくその題名の意味が理解できるようで、できないなぁ。」というタイトルの面白さから購入したおすすめの1冊です。読んでみた感想としては、「多様化という言葉の難しさ」を感じる内容でした。ひと昔前と比べ、人種や国籍・LGBTQなど、日本でも認知や理解が進んできているのではないかと思います。しかし、この本の中ではそんな人種や国籍・LGBTQ・貧困などのいわゆる社会的問題が物語の軸となる作者の息子の周囲(中学校)では当たり前のように存在しているということを前提に話が進められていきます。そして、多様化が当たり前となったからこそ、移民が移民を差別するなどの少し複雑な問題も息子の周囲では起こっていくため「どうしてそんなことをするの⁉」と感じてしまうシーンもありました。ですが、「そんな考え方もあるんだ」という新たな刺激にもなる本だと考えるのでぜひ皆さんも読んでみては?
専攻科保育専攻 伊山結子さんおススメ
「ジヴェルニーの食卓 」
著:原田マハ 出版社:集英社
表紙と素敵な題名に惹かれ、悩んだ末手にとって読んでみました。
この本は、印象派画家たち4人の人生を彼らに関わった女性たちが語る物語です。ハッとするような表現や心の中にすっと落ちてくる言葉の使い方、画家たちの絵にかけた想いが痛いほど伝わってきます。
「この花をこの花瓶に活ければ、先生が恋をなさるのではないかと」
これは私の一番好きなセリフです。読み終えた時には、きっとモネやマティスの絵を見たいと思っているはず!どの季節に読んでもピッタリな物語です。是非、読んでみてください。
専攻科保育専攻 岡みなみさんおススメ
「公務員試験のカラクリ」
著:大原瞠 出版社:光文社
私が本書を選択した理由は、実際に私が公務員試験を控えていたからです。この本を読み、少しでも公務員試験について知ることで就職に役立てることができると思い、読んでみることにしました。
本書は、試験の難しさと独特のクセから特別な対策が必要な公務員試験について、受験生、大学、教育産業、役所のそれぞれの視点から解説しているものです。
公務員試験について知ることを目的に読んだ本でしたが、そもそも公務員試験を受けると決めたことで民間就職を視野から外し、自ら選択の幅を狭めている可能性があることに気が付くことができました。この本に出会えたことで自身の就職について様々な角度から考えることができ、自分のやりたいことや適性を考えた上で志望先を決定することに繋がったと思います。
私のように公務員を視野に入れている方はもちろん、就職に関して悩みや不安を抱えている方にも読んでほしい一冊です。


